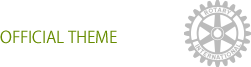Slide1テーマ:糖尿病について
皆さんこんにちは。今日は糖尿病の看護に携わっていた経験から少しでも皆さんに役に立てる情報を提供したいと思いまして資料を作ってきました。
slide2今日の内容です。 まずは世界や日本の現状について 「糖尿病とは何か?から始め、インスリンの役割について 次に、慢性高血糖が体に与える影響についてその次は最近の研究の結果の紹介と 最後に、ご自身のリスクをチェックしてみる。という感じの流れで進めていきます。
Slide3世界の糖尿病有病率(成人20‑79歳)
世界の糖尿病患者数 約5億8000万人(IDF 2025)これは世界の成人の11.1%(およそ9人に1人)にあたります。 中国(約1.41億人)、次いでインド(約7420万人)、米国(3220万人)、インドネシア、ブラジル、日本などが上位10位に入っている。
Slide4日本の糖尿病患者数と有病率
2021年時点で日本国内の20~79歳の成人の約11.0百万人が糖尿病を患っており、成人の約10–11%、厚労省の調査によれば「明らかな糖尿病者」男性7.14%、女性4.50%、糖代謝異常(前糖尿病)も15%前後)
Notes:
2021年時点で日本国内の20~79歳の成人の約11.0百万人が糖尿病を患っており、有病率は成人の約10–11%であるとになっています厚労省の調査によれば「明らかな糖尿病者」は男女で若干差があり、男性7.14%、女性4.50%、さらに糖代謝異常(前糖尿病)も15%前後に上がっていると明らかになっています。このように、糖尿病は誰でも発症する可能性がある身近な病気です
Slide5
定義:糖尿病は、インスリンの作用不足または分泌不足により、血糖値が慢性的に高くなる病気。
1型糖尿病(約3%) - 主に若い年代に発症 - インスリンの分泌不足
2型糖尿病(約90%) - 主に大人に多く見られる - インスリンの効きが悪くなったり分泌量が 不足する。
Notes:
では糖尿病はなぜ発症するのかについてここから話します。糖尿病は、インスリンの作用不足または分泌不足 血液の中の「血糖値」、つまり血液中の糖分の量が慢性的に高くなる病気です。大きく分けて2つのタイプがあります。 1つ目は「1型糖尿病」です。これは、主に若い人に多く見られるタイプで、インスリンというホルモンがほとんど出なくなることで発症します。日本では全体の3%ほどです。 2つ目は「2型糖尿病」です。これは大人に多く見られるタイプで、全体の9割を占めます。インスリンの効き目が悪くなったり、分泌される量が足りなくなることで発症します。 ちなみにモンゴルでは、2型糖尿病が全体の8割以上を占めています
Slide6
インスリン作用不全:細胞がインスリンに反応しにくくなる(インスリン抵抗性)。
インスリンとは? 体の中での働き
インスリン分泌不足:膵臓のβ細胞からのインスリン分泌が低下。
これらが単独または組み合わさることで慢性高血糖が生じる。
Notes:
インスリン体の中での働きについて説明します インスリンは、膵臓から分泌されて血糖値を下げる働きをしている大切なホルモンです。 食後は体の中で血糖値が上がり、すると膵臓β細胞からインスリンが分泌されます。 血液中の糖分を、肝臓、筋肉や脂肪の細胞に取り込ませることで、血糖値を下げる働きをしています。 このインスリンがしっかり働いている状態が「正常」です。ですが、「1型糖尿病」の人は、インスリンそのものがほとんど出ません。「2型糖尿病」の人は、インスリンは出ていても、うまく効かなくなったり、出る量が足りなくなったりしています。血糖値が高いままになってしまうのが糖尿病です。
Slide8
Source: American Diabetes Association. (2024). Standards of Care in Diabetes 2024
慢性高血糖が体に与える影響
AGEs(終末糖化産物)の蓄積 → 蛋白質の硬化・機能低下、炎症:免疫活性化 → 動脈硬化促進
細小血管:網膜症、腎症、神経障害
大血管:心筋梗塞、脳梗塞
Notes:
高血糖が慢性的に続くと、糖とタンパク質が結びついてAGEsさんぶつが血液の中に蓄積しAdvanced Glycation End Products、血管や組織が傷つきます。 その結果、目・腎臓・神経の細小血管障害や心筋梗塞など、のよく言われている糖尿病さん合併症が起こってしまいます。代表的なものは以下の3つです: 糖尿病網膜症:目の網膜の血管が傷み、結果的に視力障害や失明の原因になります。 糖尿病腎症:腎臓の機能が低下し、人工透析が必要になることもあります。 糖尿病性神経障害:手足のしびれや痛み、感覚の低下といった症状が現れます。 血糖値が高いだけの「軽い病気」と捉えられることもありますが、実際には全身管理が必要な慢性疾患ですので早期発見と血糖コントロールが極めて重要です
Slide 9
1. 体重コントロール
体重の5〜7%減好ことで耐糖能異常から糖尿病への進行を抑制 Tumblehome al. (2021).
2. 食事の改善
地中海食や高食物繊維食は糖尿病発症リスクを20〜30%低下(多くのRCTとメタ解析)
糖質・脂質を控え、野菜・魚・大豆製品を積極的に。
📌ポイント:「量」よりも「質」+「タイミング」
3. 定期的な運動
週150分以上の中強度運動で発症リスク58%減(米国Diabetes Prevention Program)
筋トレも併用で、インスリン感受性が改善します。
4. 定期健診と自己測定
HbA1cや血糖自己測定は早期発見と管理に有効(ADA 2024推奨)
ADA (2024). Standards of Care in Diabetes
糖尿病予防と自己管理の科学的根拠
こちらでは糖尿病予防には科学的に証明されたevidenceを紹介します毎回言われる基本的なことではありますが実は継続するのが難しイトいう現実もあります。体重のコントロール食事でのなかで、特に食物繊維は腸内環境の改善にもつながります。運動は週150分以上の中強度運動で発症リスクを半減させることが分かっています。さらに定期健診と血糖自己測定は、早期発見と管理の有効です。
Slide 10 最新の研究例 Source: Nagoya University, 2021; 2025.
脂肪肝と糖尿病の関連:砂糖の過剰摂取によって腸内細菌叢が変化し、脂肪肝および高中性脂肪血症を引き起こすことを実験で分かった。脂肪肝は肝臓のインスリン抵抗性を増加 → 空腹時高血糖につながる
Notes:
ここでは糖尿病に関する最近の研究の結果を共有したいと思います 最近の研究では、砂糖の摂りすぎが脂肪肝や高中性脂肪血症 こうちゅうせいしぼうけっしょうを引き起こすだけでなく、腸内細菌のバランスにも影響することが分かっています。この腸内細菌の変化が炎症や代謝異常を促進し、さらに脂肪肝や糖尿病リスクを高めると言われています。 つまり、肝臓に脂肪がたまるとでのインスリンの効きが悪くなり、血糖を下げる機能が低下します。その結果、空腹時でも血糖が高くなりやすくなります
Slide 11最新の研究例
腸内細菌と糖代謝:腸の中には100兆個以上の細菌がいて、血糖値や体の炎症に関わる。善玉菌は食物繊維を発酵させ、短鎖脂肪酸 (short chain fatty acids) という物質を作る。短鎖脂肪酸が糖代謝への関わり:
インスリン感受性を高める
ホルモン分泌の調整 → 血糖を下げる、→ 食欲を抑える
炎症の抑制
腸内環境の乱れが炎症やインスリン抵抗性を悪化させ、糖尿病や心血管疾患のリスクを高める
Notes:
続きまして、腸内細菌と糖代謝 とう代謝の関係を見ていきます。 腸の中には100兆個以上の細菌が存在し、その中の善玉菌は食物繊維を発酵はっこうして短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)とういものを作ります。短鎖脂肪酸はインスリンの効きを高め、分泌を促し、食欲も抑えます。さらに炎症を抑える働きもあります。逆に、腸内環境が乱れると炎症やインスリン抵抗性が悪化し、糖尿病や心血管疾患のリスクが上昇します。 そうすると大事なのはと食物繊維をたくさん摂ることで善玉菌が このたんさしぼうさんを作って、で血糖コントロールを助けますということですね 生活の中で短鎖脂肪酸を増やす研究者の推奨すいしょうしている方法を次のスイラドで紹介します。
生活の中で短鎖脂肪酸を増やす方法(研究者の推奨含む)
- 水溶性食物繊維を増やす
- 海藻、オート麦、大麦、豆類、野菜、果物(特に皮ごと)
- 1日18〜20g以上が推奨(日本人平均は不足)
- 発酵食品を摂る
- ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ
- 有益菌を直接摂取でき、腸内環境を整える
- 精製糖・超加工食品を減らす
- 善玉菌を減らし、悪玉菌を増やす原因になる
- 多様な食材を組み合わせる
- 腸内細菌の多様性を維持(野菜・穀物・発酵食品・発酵飲料など)
Slide 12 最新研究例
Source: A Novel Paradigm Linking Gut Dysbiosis, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, and Metabolic Dysregulation, Nagoya University, 2021
Notes:
この短鎖脂肪酸を増やすために日常生活でできることは食物繊維や発酵食品を毎日取り入れることが、腸内環を整えてくれることをわかりました。まず、野菜・豆類・海藻・果物など、食物繊維の多い食品を多く摂ること。さらに、ヨーグルトや納豆などの発酵食品も腸内環境を整えるのに効果的です。こうした食習慣の積み重ねて腸内環境と肝臓を健康に保つことで、糖尿病の予防・管理がうまくできます。
Slide 13 あなたは2型糖尿病のリスクがありますか?
0点:約65.8kg未満
1点:約65.8〜78.5kg
2点:78.9〜104.8kg
3点:約105.2kg以上
Notes:
こちらは、アメリカ糖尿病協会が作成した“2型糖尿病リスクチェック”です。自分が糖尿病になりやすい体質かどうか、簡単に確認できるすクリーニングツーるです。 年齢、性別、妊娠糖尿病の既往、高血圧、家族歴、運動習慣、そして体重ト身長のバランスから点数をつけます。合計スコアが5点以上の方は、糖尿病の発症リスクが高いとされており、医療機関での検査をおすすめしています。 このチェクが生活を見直すきっかけとしてご活用できるかと思います
Slide 14
👉 今日から1つだけでも改善できることを考えてみましょう!
生活習慣チェック(行動の見直し)